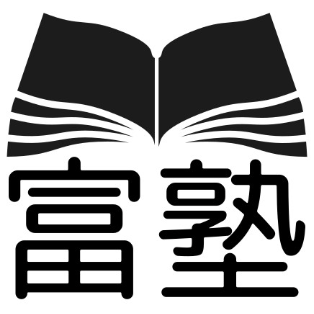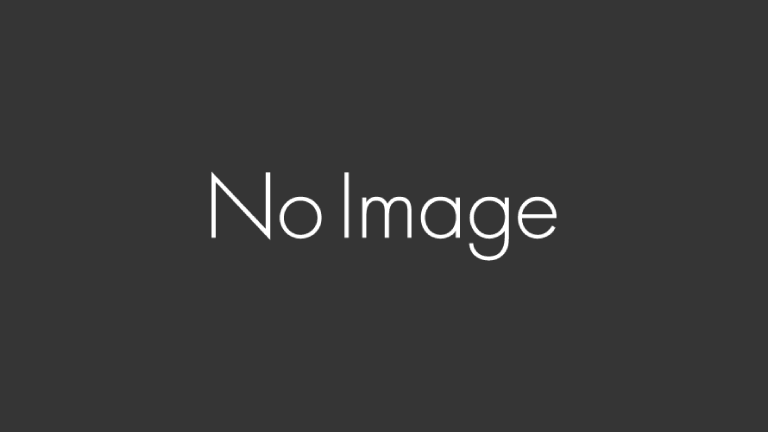はい、今回は私が実際に東大受験の時に使っていた、参考書、教科書、問題集などを紹介していきます。
今画面に写っているのが、実際に使っていたものですね。他の科目に比べるとかなり量があるかと思います。数学はやっぱり一番勉強時間が多くなる科目なので、このくらいにはなります。
一番左側が教科書、学校で配られた教科書と傍用問題集ですね。私は一般的な塾での講義は受けていなくて、学校の授業よりも先取りして勉強したかったので、基本的には教科書を使って早めに勉強していました。教科書を読んで定義を覚えて、例題を解いて、その後の練習問題を解いていく、という感じです。
問題集は、宿題でどうしても解かなきゃいけない時以外は使いませんでした。教科書の例題や練習問題くらいの難易度なので、あまり数をこなしても手応えがなく、力が伸びる感じもあまりしませんでした。
高校1年生の秋頃、教科書を全部読み終わる少し前に「1対1対応の演習」を6冊買って勉強し始めました。レベルで言うと、教科書レベルから標準問題レベルへ、という段階ですね。「1対1対応の演習」や、チャート式もこのレベルに入るかなと思います。
高1、高2の間はずっと「1対1対応の演習」を解いていました。「1対1対応の演習」の内容については、また別の動画で詳しく説明するつもりですが、全部で6冊、例題も合わせると750題ぐらいあったと思います。主に下の演習問題を解いていました。少ない問題数で、過不足なく色々な形式の問題を網羅している教材だと思います。
「1対1対応の演習」の問題が一通り解けるようになったら、応用問題レベルの問題集を解くようになりました。
現役の時は「東大の理系数学」は使っていなかったんですが、浪人期に買って、ずっと解いていました。東大の出題形式にかなり慣れることができました。
応用問題はどうしても解けない問題が出てきますが、深追いするのは良くありません。バツのままになっている問題も多少ありましたが、最終的には何周かして、知識を組み合わせながら解く力はついたと思います。
個人的に愛用していたのは「上級問題精講」です。これは「標準問題精講」のもう一つ上のレベルで、解答がかなり丁寧です。
あとは、「大学への数学」シリーズの、1対1対応よりも少し難しい問題が載っているものもいくつか買いました。
数学は勉強量が多かったので、参考書も多くて紹介するのが大変でしたが、重要なのはこれらを一通りやりきるということだと思います。
一般的な東大受験生は、相当な問題数をこなして知識を入れないといけないと思うので、一つの目安として、このくらいの参考書を3,4,5周する、という感じを参考にしていただければと思います。
以上です。ありがとうございました。